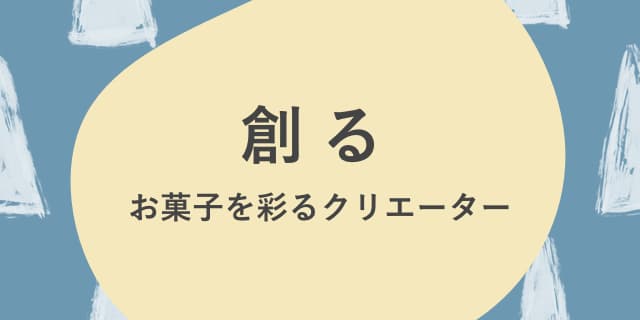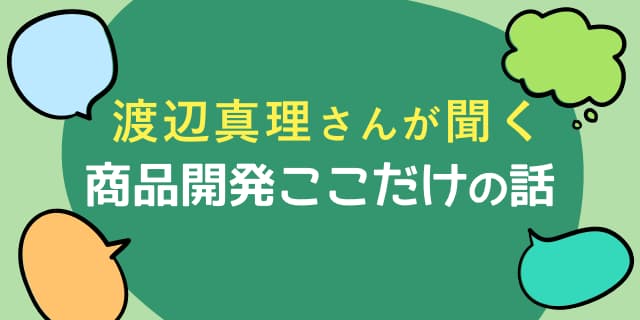与えられた場所でいつも喜んでいたい(前編)エッセイスト・作家 阿川佐和子さん

エッセイスト、小説家、インタビュアー、女優と、様々な顔を持つ阿川佐和子さん。ベストセラー本「聞く力」の著者であり、聞き手の名手として知られていますが、話術にも長けた方。阿川さんの軽妙な語り口と説得力ある言葉に引き込まれ、気がつけば1時間半にも及ぶロングインタビューに。盛りだくさんのお話を2回に分けてお届けします。
〝何の役にも立たないこと〟が面白い
——阿川佐和子さんは作家のほか、インタビュアーや女優業と多方面でご活躍されています。20代の頃は織物職人を目指していたそうですが、どういう経緯でテレビ業界に飛び込みキャリアを重ねていったのか、お聞かせいただければと思います。
若い頃は専業主婦になることが最終目的でしたから、織物職人を目指しながらもお見合いを繰り返していました。ですが、いくら回を重ねても相手が見つからない(笑)。そんな20代後半のある日、「テレビの情報番組のリポーターをやりませんか?」と声をかけていただいた。期間も2週間と短かったので、「いいお相手がいるかも~」と思ってバイト感覚で引き受けたのですが、今度は報道番組のアシスタントのお仕事をいただいて。やれと言うならとりあえずやってみるか、と。案の定最初は怒られてばかりでした。
——やめようとは思いませんでしたか?
だって結婚相手が見つからないんだもん。目的地に着けないのだから、自分で稼がないと仕方がないじゃないですか(笑)。
当時、私は実家暮らし。「親の庇護(ひご)から抜け出して経済的に自立しないと、一人前なことは言えないぞ」と思っていたので、専業主婦になれないなら、まずは経済的自立だな、と。怒られながらも仕事を続けた結果、30歳にして経済的自立を果たし、親元を離れました。
とはいえ最初は、経済的依存をする相手=亭主を見つけて専業主婦になり、自分は家事全般、育児全般を担当する、といった〝古き専業主婦〟が私の身の丈にあった一番の幸せだろうと信じていました。だから、怒られる度に「これは仮の姿。いつか抜け出す日が来るはず!」と思っていました。でも、そのうち縁談もすっかりなくなって(笑)。
——目的地にたどり着けなかったわけですね。
そう。結婚相手は見つからないし、仕事では「来年こそは一人前になれ!」と言われながら半人前のまま。そのまま番組自体が終了してしまい、私は30代後半になっていました。
すると今度は、筑紫哲也さんがキャスターを務めていた報道番組『筑紫哲也 NEWS23』のアシスタントのお話をいただいた。時事問題や報道は自分には合わないと思いつつ、そのときも望んでいただけるならやってみるかと思って始めました。ところが2年ほど経った頃、気づいてしまった。やはり私には向いていない仕事だな、と。
——それで『筑紫哲也 NEWS23』を降りられたのですね。
番組を降りたいと伝えたとき、周りからは「結婚が決まったのか?」「ほかの局から呼ばれているのか?」と問われたので否定すると、「君は何がしたいんだ?」と怒られました。「君はまだ何にもなれていない」「筑紫さんの隣に座りたい女性は山のようにいる」とも(笑)。もちろん慰留を求めて言ってくださったわけですが、「どうぞ、どうぞ、やりたい人にお譲りください」という心境でした(笑)。
——筑紫さんの隣にいる硬派な阿川さんの印象が強く残っているので、とても意外です。
「ここまで上り詰めた」みたいなことは全然実感としてなかったし、そういうことに未練がないんです。
初めて報道番組のアシスタントのお話をいただいたときも、隣に座ってうなずいていればいいんだと思って始めたくらいですから、そんないい加減な女がやるよりは、ほかにいるもっと立派な女性キャスターが担当するべきだろう、と。
それを実感した番組がありました。女性キャスター3名にスタジオで自由に語らせるという企画だったのですが、彼女たちが仕事に対する誇りや、キャスターになって良かったことなどをお話しされているオンエアを見て、その番組への出演依頼をお断りしていた私は、「出なくて良かった!」と。私はあの場にいる人間じゃない、と思いました。

——ほかの女性キャスターと何が違うと思われたのでしょうか。
報道番組に携わるようになってから、ジャーナリスティックにものを見ることの大切さは教えられたし、確かにそうだとは思ったんです。ただ、現場を取材し、現場で起きていることを伝え、そこに何が必要で何を問題視するべきかを伝えることに、気概を覚えるようなことが私にはないな、と。もちろん今起こっている問題について、憂いたり悲しんだり腹が立ったりすることはいっぱいあるけれど、それを多くの人に伝え、心を動かし、奮い立たせたい、とまでは思えない。つまり、ジャーナリストになる〝質(たち)〟ではないと思ったんです。
『筑紫哲也 NEWS23』を辞めるとき、「君は何を面白がるんだ」と聞かれて答えたのですが、〝世の中の何の役にも立たないこと〟が私には面白い。そうした、〝どうでもいいようなこと〟を「面白いよね」と人に伝えられたら、うれしいな、と。
(思い出し笑いをしながら)この前、ラジオ番組でご一緒しているふかわりょうさんに、〝ひざカックン〟をしたんです。ばれないように後ろから狙ったんだけど、見つかっちゃって。迷惑がられたけど、あれは面白かったなぁ。そんな感じなんです(笑)。
「つらいつらい」のあとが達成感に
——『筑紫哲也 NEWS23』を降りられた後、米国に渡り、1年後に帰国されてから再び報道番組のキャスターを務められました。心境の変化が?
アメリカでボ~ッと過ごして帰国したので、収入源はほそぼそと書いていたエッセイだけ。そんなときに『報道特集』のキャスターのお話をいただきました。アメリカに渡る前、自分がやりたい方向は報道ではないと思ったのは確かなのですが、一方では、取材に出かけたり、ニュースを読んだりといった一つ一つの作業自体に面白さは感じていた。報道でたたき上げられたので、そういった職人技みたいなものが少しは身についていましたし。
また、お話をいただいた番組は、現場を取材することがメインの仕事だった。報道では現場に行かないとわからないことがたくさんあると思っていたので、現場を取材することへの魅力を感じ、引き受けてしまいました。
ところが以前にも増して報道畑の方が多く、〝体を張る〟現場は想像以上に厳しかった。ボスニア紛争や世界遺産登録された白神山地の取材にも行きました。結果、1年半で音を上げました(笑)。当事者ではない私が、現場で見聞きした当事者の気持ちをコメントにまとめ、カメラに向かって伝えることが私には苦手なのだ、と。やっぱり報道番組のキャスターは向かないということを再認識しました。
——インタビューの仕事が増えるのはその頃からですか?
そうですね。報道番組を辞める頃から執筆の仕事が増えていたのですが、あるとき、『週刊文春』から連載対談(「阿川佐和子のこの人に会いたい」)でインタビューをしないかとお話をいただきました。それまでインタビューは褒められたことがなかったので、自信はなかったのですが、声をかけてきたからには責任を取ってくれるだろう、と(笑)。鍛え上げてくれることを期待して受けました。
——インタビューするのは好きですか?
好きじゃありませんよ。

——即答ですね(笑)。
もちろん「こんなに素敵な人だったのね~」とか「あら、いろいろなことを考えていらっしゃったのね」とか、発見はたくさんあります。ただ、インタビューが自分に合っているとは思わないし、いまだにうまくやれる自信はなくて。実際、うまくいかなかったって思うことのほうが多いですから。
——では、書くことは好きですか? 『聞く力 ―心をひらく35のヒント』はベストセラーになりました。その後もエッセイや小説を精力的に発表されています。
書くことも好きじゃないですよ。小説家の娘なのに読むのも好きじゃないですし(笑)。ただ、私は人から書いてみませんか?と求められることがうれしくて、引き受けてしまう。そのあとに失敗したと思うんだけど、「引き受けたくせに書かないのか?」と怒られるのはもっと怖いから頑張る。そうして必死に書くと、時々褒められるので、つい調子に乗って引き受けちゃう。その繰り返しです。
それに、ぶつぶつ文句言いながら書いていても、仕上げたときの達成感はある。書く、褒められる、そしてまた書く、を繰り返すことを結構喜んでいたりするんです。ほら、学校の定期試験が終わると、すごくうれしいでしょ? その喜びは、「つらいつらい」を乗り越えたからこそ得られるわけじゃないですか。それと同じで、「つらいつらい」のあとの「やった!」という達成感を得ることは、私にとって必要なことなのだと。〝仕事をする〟というのは、そういうことだと思ったわけです。
——キャリアを重ねるとともに、「専業主婦が自分の身の丈に合った一番の幸せ」というお考えは変わってきた、と?
文春の対談が始まったのがちょうど40歳なのですが、その頃から、結婚しても仕事は辞めないぞと思うようになっていました。
インタビューや執筆の仕事は、その場では一人での闘いですが、担当編集者はもちろんのこと、インタビューであればゲストもいますし、撮影カメラマン、録音担当者といった仲間が「いいものを作ろう」という同じ意識で動いている。「これ面白いね」と言い合いながらプロジェクトを進めていくことは楽しいし、その評価として、お褒めの言葉やお金をいただける。それこそが生きる意義なのだと思えたことが大きいと思います。
心の引き出しを探る文章が書ければ幸せ
——ところで、6月末に発刊された小説『ブータン、世界でいちばん幸せな女の子』をとても面白く拝読しました。最後、ほろっとして、心温かい気持ちになりました。
ありがとうございます。文藝春秋社の小説誌『オール讀物』で〝女ともだち〟をテーマに書いた6編をまとめた短編連作集になります。1話目を書いたのが2017年、最終話を書いたのが2022年と5年もかかってしまいましたが。
——なぜそんなに時間が?
出版社の人事の関係で編集担当者が3回代わりまして(笑)。連作がスタートした当時、仕事のほかにも更年期障害や親の介護と様々な理由でとても忙しかったんです。そのため、担当者と毎月は無理だろうから書けるときに書いて、ゆくゆくは一冊にできたらいいね、と話していたのですが、その後、書いて出すと連絡が途絶え、担当者が代わる、というのを繰り返しました。時間が経つと、前回書いた内容も忘れちゃうし、当初のテーマと微妙にずれるし、物語を収めるのが大変。人事異動に翻弄(ほんろう)されて書いた小説なんです(笑)。
——テレビの仕事をしながら30代でエッセイを書き始めた阿川さんですが、46歳で小説家デビューを果たしました。何かきっかけが?
私が米国から帰国した後、以前から飲み友だちだった編集者が小学館の『本の窓』(出版社が自社の書籍を宣伝するPR誌)に異動になっていて、「阿川さん、そろそろフィクション書きませんか?」と提案してくださったんです。以前、彼と飲んでいるときに、エーリッヒ・ケストナー(ドイツの作家・児童文学作家)みたいに、私もいつか子どものための物語でありながら、大人が読んでも心に残るような物語を書くのが夢だね、なんて話をしたのを覚えてくれていたのだと思います。
それで彼と話すうち、とりあえず女の子を主人公にして、その子の成長物語、つまりは朝ドラで放送されるような原作にしよう、と(笑)。どっちかというと、男の子の物語が好きだったのだけど、私は男じゃないから女の子がいいだろう、その子を語り部にして、幼稚園の場面から始めて、そこに不思議な女の子が転園してきて、2人の友情を中心にした成長物語はどうだろうということになり、連載がスタートしました。
いちいち話が長くなってすいません(笑)。
——面白いです(笑)。
転園してきた〝ウメ子〟の家族のバックグラウンドも書かなきゃいけないな、とか、語り部にした〝みよちゃん〟の家族構成も書かなきゃいけないし、とか。2人の出会いも書かなくてはと思いながら1回、2回と書いて、5回目ぐらいまで書いたら、締め切りが迫ってないのに、担当編集者から電話がかかってきて、「これ、18回で1冊分の予定なのですが、5回目で主人公たちはまだ幼稚園。いつ、小学校に上がりますか?」と聞かれた(笑)。 何の計画性もなく書いているから、言われて初めて、〝そうか3分の1近く来ちゃったのに、まだ幼稚園だ〟と気づきました。結局、最後だけ中学生にしたけど、ずっと幼稚園のまま(笑)。そうやって何の計画性もなく書いた物語が形になり、初の小説本として出版されたのが『ウメ子』です。

——坪田譲治文学賞を受賞された初の長編小説にそんな裏話があったのですね。
書籍化するときも紆余(うよ)曲折ありました。一冊にするには分量が多く大幅にカットする必要があったので、担当編集者が候補を挙げてくれたんです。見ると、ストーリーには何の支障もないところが削られていた。編集者としては当然の判断。でも、私はそこを書いているときがめずらしく楽しかった。そう伝えたら、「じゃ、残しましょう」と言ってくれました。まとめるのは本当に大変だったと思います。
——書いていて楽しかったところというのは?
例えば、ウメ子に「石ころは生きている」と言われ、ジーッと見るんだけど全然動かないとか(笑)。実はそれ、私の幼稚園時代の思い出なんです。いつか動くだろうと思って見続けたのに2時間経っても動かないとか、この大木は夜になると動き出すに違いないと想像するとか、そんなどうでもいいことが記憶に残っていたので、語り部であるみよちゃんに託して書いたんです。

——〝何の役にも立たないことを面白がる〟阿川さんらしさが表れた小説本なのですね。
今も印象に残っているのですが、『ウメ子』の取材を受けた際、「素晴らしい作品でした」とは誰も言わないのに(笑)、「これを読んで僕は自分の幼い頃の一日を思い出しました」と言ってくださる方がたくさんいた。自分の幼稚園話をするために私のところに来たみたいで、さんざん話をして帰って行くの(笑)。それがとてもうれしかった。
その時に気づいたんです。まず私は、筋書きに関係ないどうでもいい文章を書くときは、筆が進むんだな、と。そして、その文章は、〝自分や誰かの心の引き出しを探る〟役割を果たしているのかな、と。であれば、私はこれでいいや、書く意味があるのだな、と思ったことを覚えています。
それからずいぶん経つので、技術的にはもう少し上達しているかもしれないけれど、基本は、小説にしても、エッセイにしても、ばかなことを書いているなと思いつつ、引き出しを探ることにつながる文章が書ければ、十分幸せなんだなと思います。
取材・文 辻 啓子
撮影 元木みゆき
2022-08-30