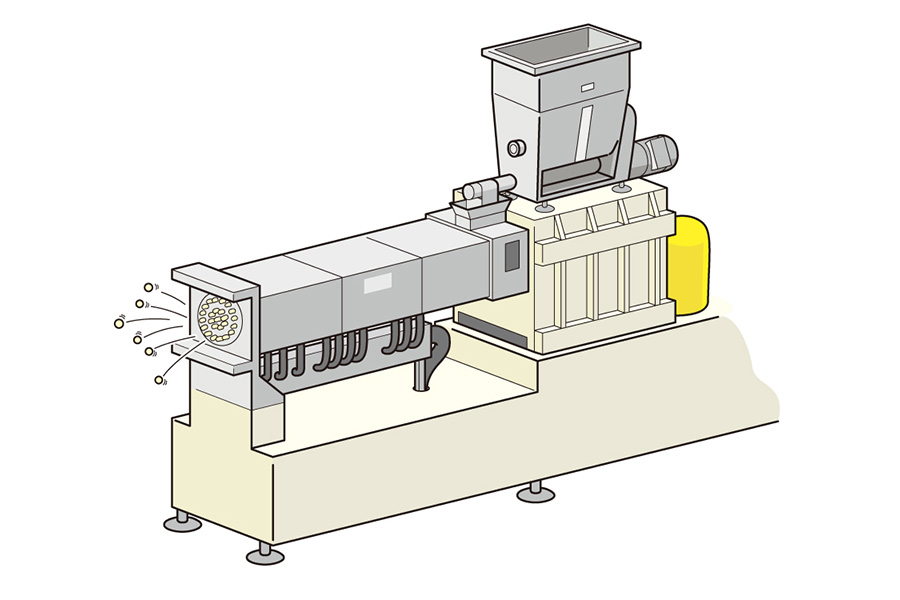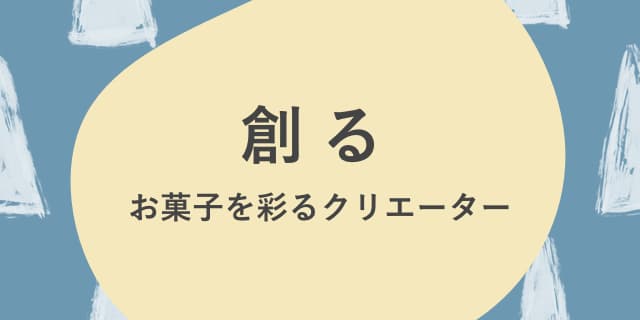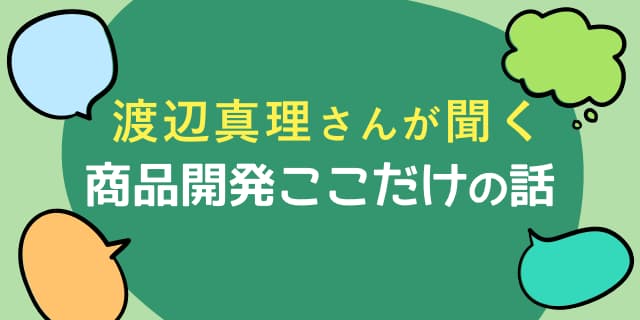“人間の本質”を追い続けたい映画監督 李 闘士男さん

映画『家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。』(2018年)をスマッシュヒットに導いた李 闘士男監督。12月17日に公開される最新作『私はいったい、何と闘っているのか』(原作:つぶやきシロー)は、頑張りがいつも空回りしてしまう、スーパー“ウメヤ”のフロア主任・伊澤春男が主人公。春男が巻き起こす悲喜こもごもの騒動を、李監督持ち前のコメディーセンスで笑いあり涙ありの感動作に仕上げました。春男と妻・律子の出会いのシーンでは、ロッテの商品「小梅」が登場。「小梅は僕にとっても“初恋の味”」と語る李監督に、撮影時のエピソードや映画制作に込めた思いを伺いました。
主人公はどこにでもいる人
——李闘士男監督は、大学卒業後、テレビの番組のディレクターとして活躍された後、2004年の映画『お父さんのバックドロップ』で監督デビューを果たされました。監督になられたきっかけをお聞かせください。
僕にとってとても大切な方から、「君の映画が観たい」と言われたことがきっかけです。この方のために映画を作りたいと思いました。正直言えば、それまで映画監督になりたいと思ったこともなかったですし、うちの嫁からは今でも「よく映画監督やっているわね」と言われるくらい映画も観ないほうなんです(笑)。
人って、自分のためより誰かのために何かしようと思ったときのほうが頑張れるというか、力を発揮できる。自分の意思で始めたことではなかったですが、結果的には監督になって良かったなと思います。
——バラエティー番組を作っている頃ですか?
そう、30歳くらいだったかな。その方は業界で恐れられている方でしたが、僕には優しくて「李ちゃん、銀座で遊ばなくちゃ!」と、高級クラブに連れて行ってくれたり(笑)。その頃の僕は、若いくせにテレビ局の偉い人と言い合ったりもしていた。そういう僕を見てくれていたのか、あるとき「あれだな、李くんのほうが楽しいし面白いな、話しているのを見ていると映画監督みたいだよ」「李くんの作った映画が観たいな。俺に力があったら撮らせてあげるんだけどな」と言っていただいたことがあって。それからですね。できるかどうかわからないけれど、この人のために映画を撮ってみたいな、と。だから今でも映画が完成したら、その方には最初に連絡をして試写状を送っています。
——その方が李監督に「映画を撮らせたい」とおっしゃった意味を、どう捉えていらっしゃいますか?
テレビに比べると、映画は監督の思いみたいなものを通しやすいので、「李くんは李くんの思いを通せる場のほうが、個性を生かせるのではないか」ということだったのかな、と。確認したことはないのでわかりませんが、たぶんそういうことだと思います。

——実際に10年以上監督として多くの作品を生み出していらっしゃいます。作品作りへのこだわりがあればお聞かせください。
こだわりというか、僕の映画は基本的に主人公を含めメインの役は死なないです。殺したくないんです。そして“徹底的な悪人”は出てこない。
——今作『私はいったい、何と闘っているのか』も、根っからの悪人は登場しません。
どんな人も、人生ってそううまくいかないんですよ、きっと。思い通りにならないことばかり続くんです。だから、意地悪な人にも、そこには理由があるんだろうと思うわけです。
今作にも女性の立場からすると“ひどい男”は登場しますが、そんなに“悪いやつ”には描かれていないでしょ? 観ている側には、彼にも彼なりの事情があるのだろう、葛藤があるのだろうと伝わるんじゃないかと。
「根っからの悪い人はいない」みたいな臭いことではないんだけど、人はささいなことで変わるものだと思っている。だから人の心というのは、幸せなんて大げさじゃなくても、ふとしたことで満たされるのかもしれないな、と。そんな人間を表現したいという気持ちがあります。
——なるほど。
今作もそうですが、僕が作る映画には事件という事件が起きません。劇中の作法としてはよろしくないのかもしれませんが、起承転結があまりない(笑)。僕自身は、半径3m以内のところを見直すことで、人生って豊かだなって思えることがある気がするんです。

——今作についてもう少しお聞かせください。この映画を監督することになったきっかけを教えていただけますか。
プロデューサーの方から、原作であるつぶやきシローさんの著書『私はいったい、何と闘っているのか』を読んでみて欲しい、李さんの監督で撮れないだろうかと提案されました。拝読したら、素晴らしい作品でした。主人公の伊澤春男は、“どこにでもいる人”で。
——先ほどおっしゃった「半径3m以内」ですね。
そうです。大きな事柄は起きない物語なので、作り手は事柄を追わなくていい。その分、人をとことん追える。読むうちに「この男の人生に寄り添いたい」と思えてきました。それが撮りたいと思った理由です。
僕はヨーロッパの映画が好きなのですが、それも同じ理由です。イタリア映画やフランス映画って、あまり大きな事件が起きないので、最初は理解しづらい。「何だろうこれ」と思いながら観進めていくと、事件が起きないので、登場人物に寄り添わざるを得ない。するとようやく映画の言わんとするところがわかってきて、また観たくなる。事柄が大きく動く映画は面白いし刺激的なのですが、何度も観たいとは思わないんですよ。本質とは、なかなか見えないところにそっと隠れているんじゃないかな。
コンテンツでは伝わらないことをやるのが映画
——前作『家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。』(以下『妻ふり』)も、どちらかと言えば、大きな事件は起こらない映画でした。ひたすら榮倉奈々さん演じるちえが死んだふりをして安田顕さん演じるじゅんを驚かせ、あきれさせるという……。
そう、一見ばかばかしい映画ですよ(笑)。
少し脱線しますけどいいですか?
——はい。
『妻ふり』の最後、「どうして私が死んだふりしたかわかりますか?」というちえの問いかけにじゅんが答えるシーンでは、風の音が大きくなり、観客にじゅんの声は聞こえません。なぜそうしたかというと、答えはひとつではないからです。映画をご覧になった方々が考えてくだされば、と思ったのです。
また、今作では、最後のほうに伊澤春男(安田顕さん)と妻の律子(小池栄子さん)が2人並んで「ばかやろう」と叫ぶシーンがあります。
実はこの2つのシーンには同じ狙いがあります。
例えば、キャンディーを食べた2人が、それぞれ「おいしい」と言ったとします。言葉は「おいしい」だけど、2人の「おいしい」には違う意味があると思うんです。「おいしい」以外、適当な言葉が見つからないから使っているだけで、100万人いれば、100万通りの「おいしい」がある。
今作の「ばかやろう」も、セリフ(コンテンツ)的には「ばかやろう」なのだけど、コンテキスト、つまり文脈や背景には「ばかやろう」ではなく、「俺は幸せだよ」かもしれないし、「俺はおまえと結婚して良かった」もあり得るわけです。このシーンでは、2人ともほぼ「ばかやろう」しか言ってないのだけど、観てくださった方々が、「この夫婦、なんかいいよね」と思ってくれればいいのかな、と。
コンテンツでは伝わらないことをやるのが映画だと思うし、それが映画の持つ力でもある。そこは信じないといけないなと思います。

——夫婦2人で叫ぶあのシーンは、原作にはありませんでした。
はい、僕が必要だと思って作ったシーンです。
——映画には原作にはないシーンや順番の異なるシーンがいくつもありました。脚本は『妻ふり』に続き坪田文さんが担当されていらっしゃいますが、どのようなお話をされたのでしょうか。
簡単に言えば、「前半はおかしく、後半はオモローてやがては……」の流れで作ろうということですね。
僕が作る映画を一言で説明すると、「昔の松竹映画をアップデートした」イメージ。人情ものを現代っぽくしたような映画だと思っていて。人情は普遍的なものだと思うので、喜劇っぽい要素を散りばめながら、後半は、観ている人の心の中に染み込んでいくエピソードを入れたい、そんな話をしましたね。
また、観ている方には登場人物のキャラクターを理解しながら物語を読み解いていってほしいと思っているので、まず主人公がどういうキャラクターなのかを見せることが大切だと。それには“キャラ”の出やすいシーンを前半に持ってくるほうがいいので、最も“空回りして見える春男”のシーンを冒頭に持ってくることを提案しました。例えば、春男がスーパー“ウメヤ”で主任として働いているシーンから始めてしまうと、“ダメなやつ”であることが観客に伝わらないでしょ?
——春男がそうめん作りで大失敗するシーンから始まるのは、“頑張っているのに空回りしちゃうダメな春男”というキャラを見せるためだったのですね。
そうです。言っていること、ちょっと監督っぽいでしょ(笑)。

——では監督に伺います、今作で一番伝えたいこととは?
先ほどお話ししたように、人生って、ほとんどの人が思い通りにいかないわけですよ。でも、そんな人生もいいんじゃない? そんな人生を肯定しましょうよ、というね。勉強ができないからダメとか出世できないからダメとか奥さんに出て行けって言われたからダメとかじゃなくて(笑)、そんな自分をいとおしく、包んであげましょうよっていう感じかなあ。そう思って僕は春男の心に寄り添いました。
映画というのは、1,800円を支払って観るたった2時間に、気分転換を求めたり何か希望を求めたりしている人たちのために存在する。そういう人たちに寄り添う映画を作ることが、彼、彼女らの人生を肯定することにもつながるんじゃないかと思うんです。
実現できているかは分かりませんよ(笑)。そんな映画になればいいなと思って作っています。
——ところで今作にはロッテ「小梅」が登場します。小梅はご存じでしたか?
もちろんです。最初の出合いは小学校2~3年生の頃かな。当時、7つ上の親戚のお姉さんによく遊んでもらっていたのですが、「口開けてみ?」と、小梅を口に放り込んでくれてね。酸っぱかったなぁ。実は僕、そのお姉さんのことが好きだったんですよ。まさに小梅は初恋の味?
僕もうまいこと言うな(笑)。
そんな原体験がありましたから、原作で春男と律子の出会いのシーンで小梅が出てきたときはすぐにイメージできました。
小梅を持ち歩いている男という設定が面白いと思いましたね。僕は大阪出身なのですが、飴を持って歩いているのはおばちゃんだから。
——「小梅」の登場シーンを撮るときのエピソードがあれば教えてください。
そりゃもちろん、小梅のアップを撮ったことですよ。ね、(取材に立ち会っていたロッテ担当者に向けて)ちゃんと撮りましたよね? カメラマンにも、「ロッテさんが来てはるよ、アップ撮ったほうがいいんじゃないの?」って。サービス満点でしょ?(笑)
——春男を演じる安田顕さんは、『妻ふり』でも主人公を演じています。今作でも安田さんを起用した理由をお聞かせください。
安田さんの演技って、頑張れば頑張るほど情けない感じがいいんです(笑)。頑張っている姿が格好良く見えるのではなく、頑張っているのになぜか情けなく見える。そして、更にその姿がチャーミングに見えるという希少な役者さんです。人間のダメな部分を演じながら、チャーミングに見える人って最高なんじゃないかな。
幼少期から光っていたコメディーセンス

——昨今、エンタメ業界を取り巻く環境はがらりと変わりました。何か思うことがあればお聞かせください。
そんな大それた事を言える立場ではないのですが、最近、思ったのは「お猿さんはいくら頑張っても芸術は生まないんだな」と。
——お猿さん?
お猿さんや生き物にとって大事なのは“今日の餌”で、「来年はどうしようか」なんてことはおそらく考えませんよね。対して人間は、一年前になぜあんなことをしたんだろうと後悔したり、自分は一年後どうなっているのだろうか、と悩んだりします。人間は、そうした不安にさいなまれ、心に葛藤が生じるわけですよ。彼女のことは好きだけど、俺は既婚者だしな、とか、会社を辞めたいけど社長には世話になったからな、などと葛藤する。そんな人間の心の葛藤に必要だったのが芸術だったのかな、と。ある人は音楽で表現し、ある人は文学や絵画、映画で表現したんじゃないかと思ったわけです。だとすれば、人間から葛藤というものはなくならないはずなので、芸術もなくならないし、常に人に寄り添っていくものだと思うんです。
例えば日本では戦時中、戦争をテーマに多くの映画が作られました。韓国にはいい映画がたくさんありますが、北朝鮮との関係も理由の1つだと思います。つまり、映画制作において環境は絶対的要素。戦後すぐに美空ひばりさんの曲が生まれたのもそういうことでしょう。苦しみのなかからこそ、何かを伝えたい気持ち、理解を求める気持ちというのは生じるものですから、コロナ禍にある今も、映画に限らず、多くの芸術作品が生まれると思います。
——今後、監督はどのような作品を作りたいと思っていらっしゃいますか?
最初の2~3本はこう作れば面白くなるよね、ということだけで作っていましたが、そのうち、僕はなぜ映画を撮っているんだろうと思うようになり、“自分の役割”を考えるようになりました。
何となくわかってきたのは、映画を作るってことは、哲学と一緒。「人間って何なのだろう」ということを考え、伝えていくことでしかない、という気がしています。それが僕の役割なのかな、と。
僕はそれを「サラッ」と伝えたいんですよね。ところが重厚な作りをしないと伝わらないのが辛い(笑)。
——それはなぜだと?
昔の文学青年って、自分なりに必死に考え、作品と向き合っていたじゃないですか。今は向き合ったりはせず、受け入れるだけの人が多いですよね。誰もが思うこと、画一的なものを感じとろうとする傾向が強い。だからじゃないですか?
ただ、それを否定しているわけではないんです。そういう時代に合わせて作っていかないと、とは思っています。
まぁでも、映画に出合った以上は、“人間の本質”みたいなものは追い続けたいですね。
——そこは譲らずに、ですね。
それしかできないですから。あとは“ユーモア”。追い続けたいですね。

——監督のコメディーセンスってどこで磨かれたのでしょうか。
なんですかねぇ。わからないけど、小学校低学年から、クラスで一番面白かったのは僕という自負はある。それは間違いない(笑)。それを信じてやってきました。
——最後に2つ、教えてください。まず、最近、うれしかったことはなんですか?
僕が一番うれしいのは、やはり映画を観て感想を言っていただくことですよ。今作では、「李くんの映画だな、温かいな、気持ち良かったんだよ。でもさ、あそこで長州力? あそこで出すのがずるくて好きだよ」と言われたのがうれしかったですね。
人にはさまざまな感情がありますが、映画って「泣き」と「笑い」2つの感情を同時に湧き上がらせることができる唯一の芸術なんです。あったかい涙を流しながら笑う、という贅沢は、映画だからこそのもので、それはもう、最高の体験であるはず。だから、今作を観た方がそれに近い体験をされたとわかり、うれしかったんです。
映画制作にはいっぱいお金がかかります。だから興行的に成功することは大切なのですが、人の心に入り込み、その人の人生をひょっとしたら変えられるかもしれないと思えたときは、監督冥利(みょうり)に尽きますね。
——では、好きな言葉を教えていただけますか?
いっぱいありますが、2つ挙げますね。
ひとつが、「悟りという事は如何なる場合にも平気で死ぬる事かと思っていたのは間違いで、悟りという事は如何なる場合にも平気で生きる事であった」。
「僕はいつ死んでもいいんだ」ではなく、「どんなことがあっても平気で生きる」というね、長らく病床にあった正岡子規の言葉です。
そして「一日一生」。
例えば誰かとケンカしたとします。でも、「今日が人生の終わりでこの人と会うのも最後」と思ったら相手を許せますよね。
どちらもいい言葉でしょう? どうかな?
取材・文 辻 啓子
撮影 元木みゆき
2021-12-17