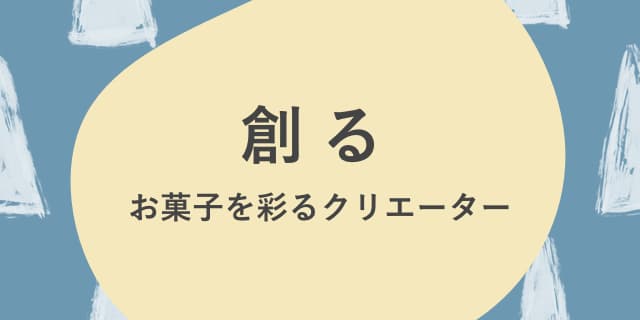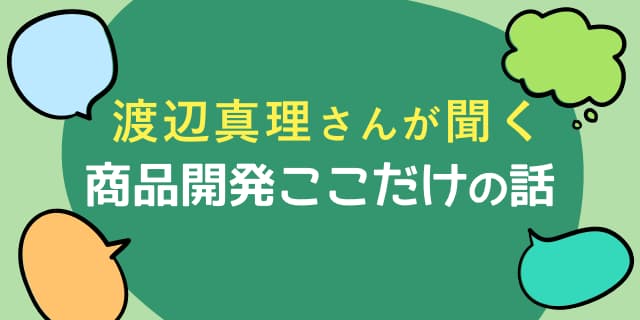エッセイ アーカイブフルーツ牛乳の味漫画家 ヤマザキマリ

音楽家でオーケストラ勤めだった母はいつも忙しく、学校から帰っても家に彼女がいることは滅多になかった。
お友達の家と違って私はランドセルに結び付けてある鍵でドアを開けなければならず、「お帰りなさい」を言ってくれる人もいない家にいるのも寂しくて、毎日外で遊んでばかりいた。
当時、母と妹と3人で暮らしていたのは北海道だったので、外で遊ぶといっても公園みたいな敷地では物足りず、男の子たちに交ざって近くの森や川に行き、そこで虫を捕まえたり川で泳いだりして過ごすのである。当然服も身体も毎日汚れ放題で、だから近所に銭湯があるのは有り難かった。
母の帰宅が早い時や休みの日は、夕方に一番風呂を目指して銭湯へ行くのが習慣になっていた。母も内風呂の狭さがあまり好きではなく、それは彼女の両親も同じだった。母はたまに実家へ戻ると立派な内風呂があるにもかかわらず、そこでも余程でない限りお湯をためることはない。せっかく目と鼻の先に銭湯があるんだから、そっちの方が狭い浴槽よりもよほど寛(くつろ)げるし、いろんな人とおしゃべり出来るから楽しい、というのが祖父母達の見解だった。その影響で母は実家を離れたあとも銭湯が近くにある住まいを選んでいたらしく、私達が子供の頃に暮らしていたその市営住宅も、まさしくその条件にかなっていた。
番台のお婆ちゃんの思いやり
その銭湯の番台にはいつも笑顔を絶やさない小さなお婆ちゃんが座っていて、私達が入って行くと「あ、子供代金はいりませんよ」と大人1人分の入浴料しか取ろうとしなかった。うちが母子家庭で、母が忙しいことを知っていたからかもしれない。ある時お婆ちゃんが「お母さんがいなくても、あんたたちだけでも来ていいんだからね、遠慮しちゃだめなんだよ」と声をかけてくれた。お婆ちゃんの孫は私と同級生でもあり、2階にあった住居から下りて来て、一緒にお風呂に入ることもあった。母も、ふたりの娘をいつも寂しく留守番させるよりは、お婆ちゃんや顔見知りの人達が世話を焼いてくれる銭湯で過ごしてもらうほうが安心だったはずである。
お婆ちゃんの厚意に甘えて、私と妹はふたりきりでも銭湯へ行くようになったわけだが、時々、お湯から上がって帰る身支度をしていると、お婆ちゃんが冷蔵庫の中にあるフルーツ牛乳を奢(おご)ってくれることがあった。「いつもふたりきりでお留守番しているご褒美」ということだったが、いまだにフルーツ牛乳を飲むとあのお婆ちゃんの優しい顔が思い浮かぶ。
他人を心の底から思いやれる人達が普通にいた時代の思い出は、私の一生の宝物である。
季刊広報誌「Shall we Lotte」第36号(2017年夏)より転載
「小さなご褒美」をテーマに、ご自身の経験から、嬉しかったことやほのぼのとしたお話などのエピソードを、読む人がちょっと元気をもらえるようなエッセイにしていただきました。
2020-03-17