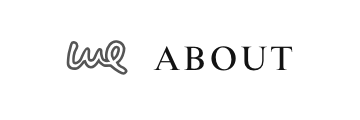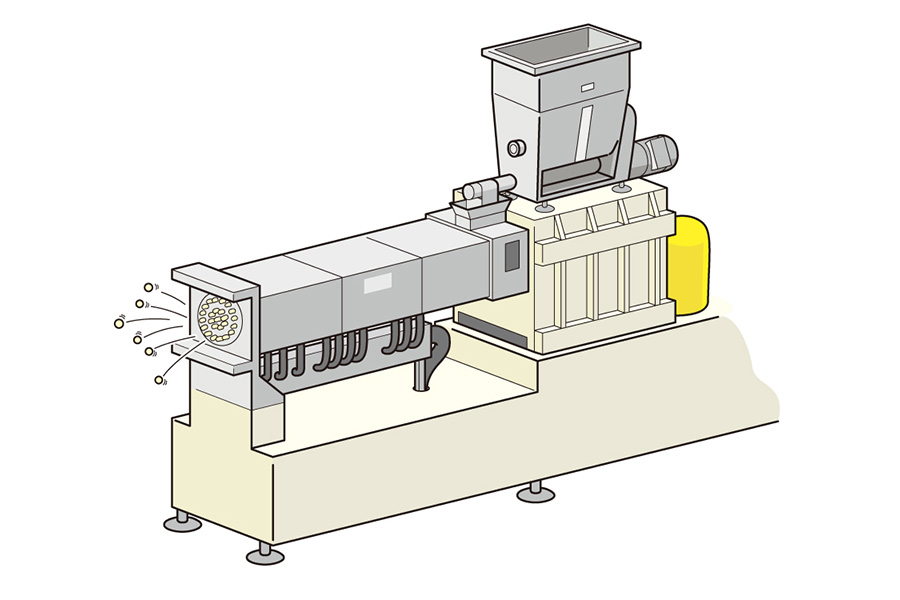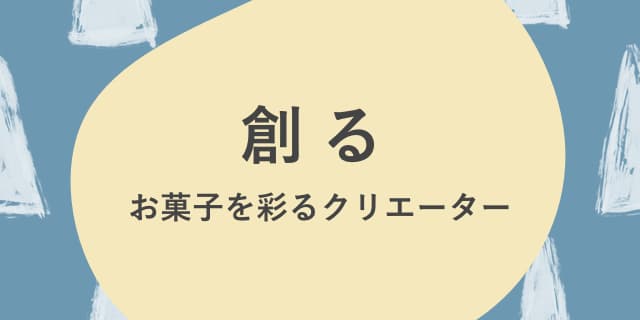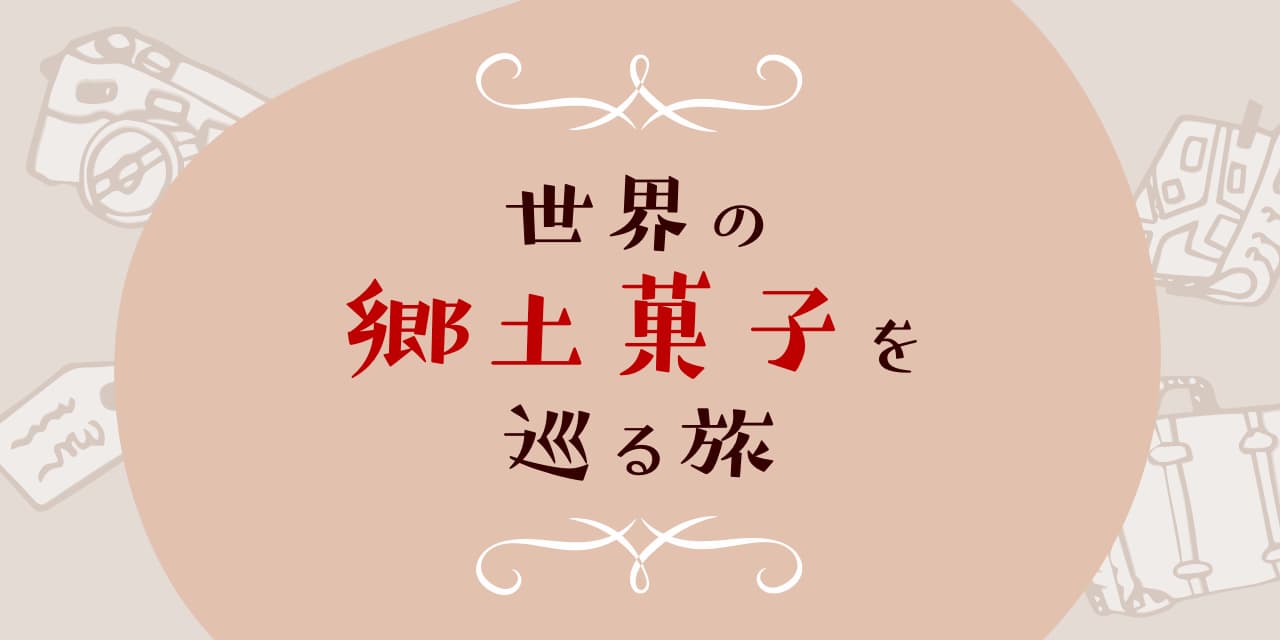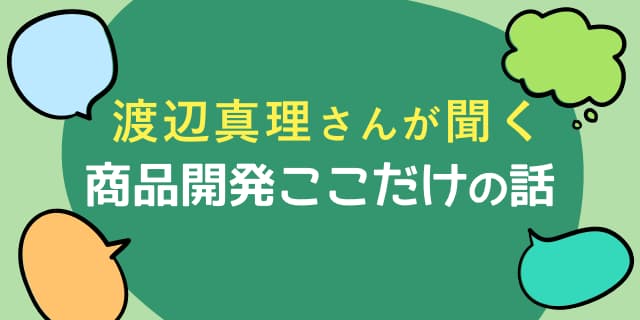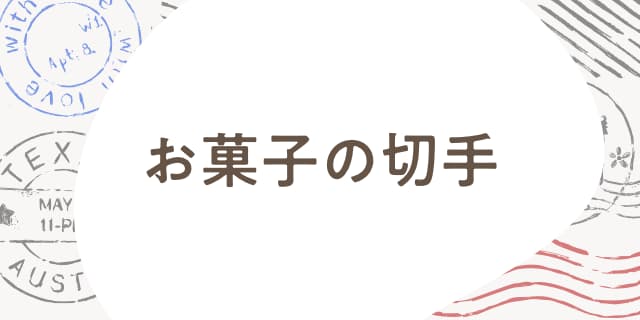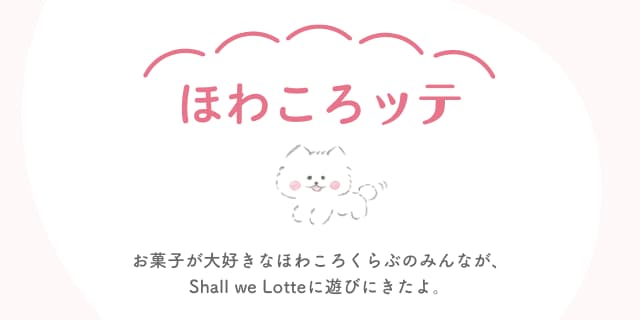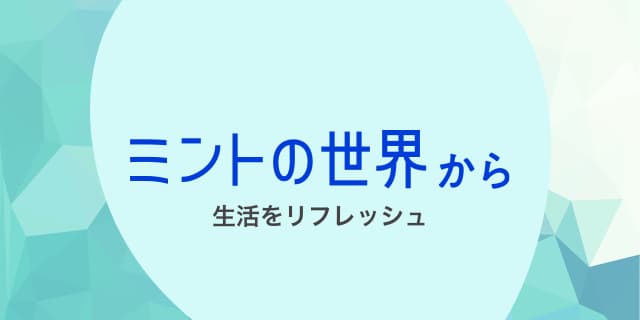最終回 ダーンタッ〔マカオ・香港〕ヨーロッパの西端からアジアの東へ伝わる郷土菓子


ヨーロッパから始まった私の自転車旅も終盤に差し掛かり、ベトナムから中国に入り、マカオを目指した。マカオはカジノのイメージくらいしかなかったが、ポルトガル領だった時代もあったので、ヨーロッパの雰囲気も感じられるのではないかと期待が膨らんでいた。というのもかつてフランス領であったベトナムにはさまざまな場所にヨーロッパのような景色があったからだ。アジアの市場なのにバゲットが並んでいた風景にはとても驚いたし、ベトナムコーヒーという新しいスタイルでコーヒー文化が育ち、洋風の建造物からもフランス統治時代の名残を感じさせられた。ベトナムの郷土菓子はココナッツミルクやパンダンリーフといった東南アジアならではの食材を使ったものが多かったが、国境を越え、中国に入ると途端に、小豆のお汁粉や豆花(トウファ)といった日本でもなじみのあるお菓子に変わっていった。グラデーションのように食文化が変化する中、マカオに入るとまた一つ中国本土とは毛色の違った光景が広がっていた。


マカオは1557年にポルトガルの居留地が設立されてから1999年までの長い間、ポルトガルの植民地であった。そのため、町にはポルトガルで見た青色のタイルや、ポルトガル語のメニュー、ポルトガル料理屋なんかを散見することができた。何世代もマカオに住むポルトガル人もおり、町中にはポルトガル人の経営するカフェも目立つ。「餅屋」や「甜品」といった漢字表記ではなく「Pastelaria」(ポルトガル語でお菓子屋の意味)の看板を目がけて入ると、ミルクがゆ「アロスコンレチェ」や生クリームとビスケットを層にした「セラデューラ」、キャラメルプリン「フラン」といったポルトガルの菓子を楽しむことができる。中でもポルトガルを代表する郷土菓子パステルデナタは欠かせないだろう。


パステルデナタはいわゆるエッグタルトのことで、世界中で大人気のお菓子の一つだ。サクサクのパイ生地に卵とミルクの甘いアパレイユ(液状の生地)を詰めて焼く。以前、パステルデナタの発祥とも言われるポルトガルの老舗「パスティス・デ・ベレン」を訪れた時、その味に感動したことがあった。青いテントのきれいなお店の前には、今か今かと自分の番が来るのを待ちわびる客が長い行列を成していた。かなりの順番待ちを覚悟していたが、思いのほか、行列はすぐにはけていった。それもそのはず、地元のお客さんはパステルデナタを頬張るやいなや、エスプレッソで流し込み、そそくさと帰っていくのだ。まるで、サラリーマンが鉄道駅のホームでそばをかき込むかのような勢いだ。それだけ客の出入りがあるので、常に、厨房から焼き立てサクサクのパステルデナタが運ばれてくるのだ。

そんなポルトガルで生まれたパステルデナタはマカオでは蛋撻(ダーンタッ)という名前で親しまれている。卵を意味する「蛋」とタルトと似た発音の「撻」でダーンタッと命名されたそうだ。マカオのカフェでもよく目にする他、蛋撻をうりにしている専門店もある。お隣、香港にも同様に蛋撻は売られていたが、マカオのものと表面に大きな違いがあった。マカオのものは表面が香ばしく焼かれているが、香港のものは焼き色を付けず白く仕上げられていた。個人的には香ばしく焼かれている方が好みだが、優しく焼かれているのが好みの人もいるだろう。その違いに良し悪しはないが、マカオで売られていたものを見て、蛋撻にもポルトガルのDNAが色濃く伝え継がれていることを感じた。

郷土菓子の魅力は地元の人のこだわり詰まった思い
ヨーロッパの西の端ポルトガルからアジアの東マカオに伝わったパステルデナタのように、郷土菓子には歴史をひも解くと見えてくる面白さがある。遠く離れた土地で同じお菓子がたしなまれることもあれば、地続きでも、宗教が違えば郷土菓子もがらりと変化するし、気候や土地によっては食材も大きく変化する。
長年愛され、伝え継がれてきた郷土菓子は結局のところ素朴で無駄がない。余計なことは時代と共に排除されていくのかもしれない。地味でも素朴でもこのお菓子は「こうでなくちゃ」「おいしいよ」と自信をもって胸を張れる、そんな地元の人たちのこだわりの詰まった思いこそが郷土菓子の魅力なのだ。




2022-03-22