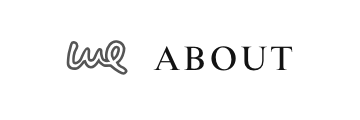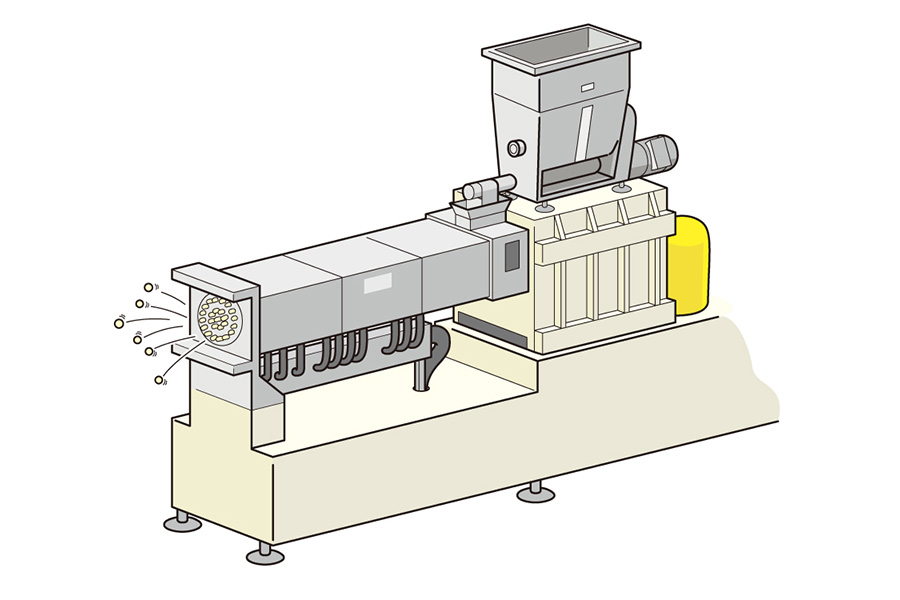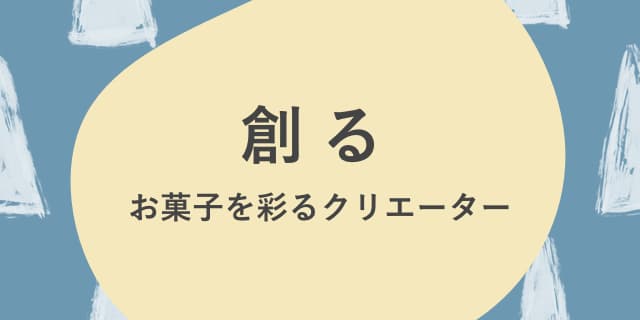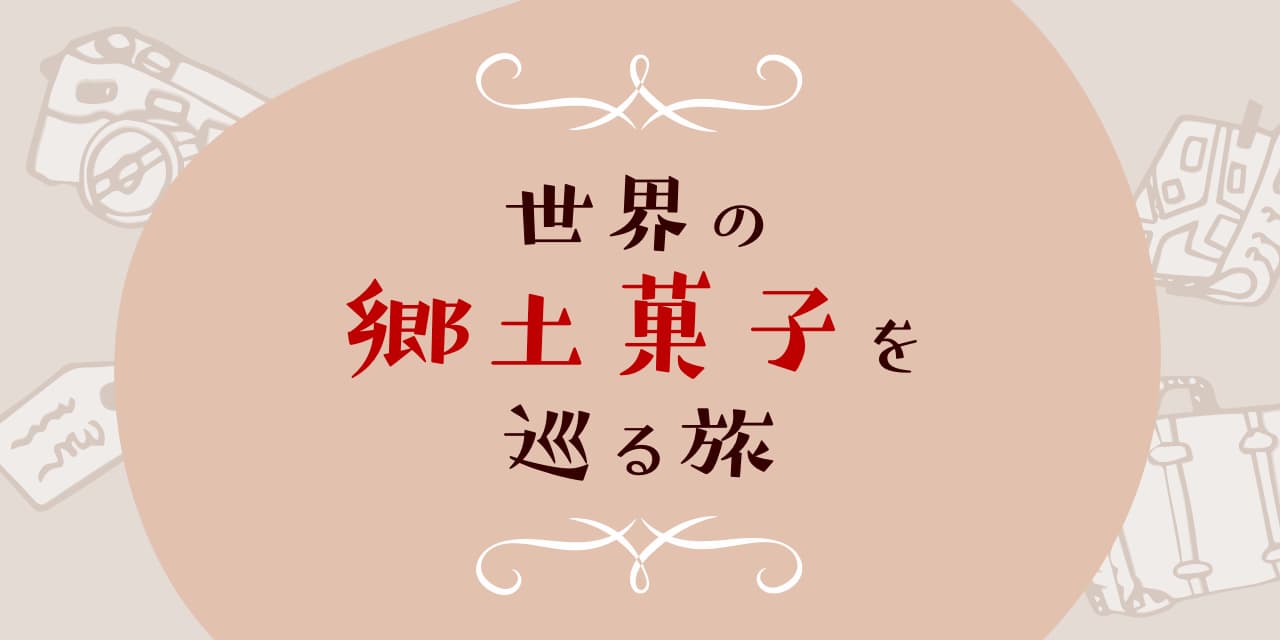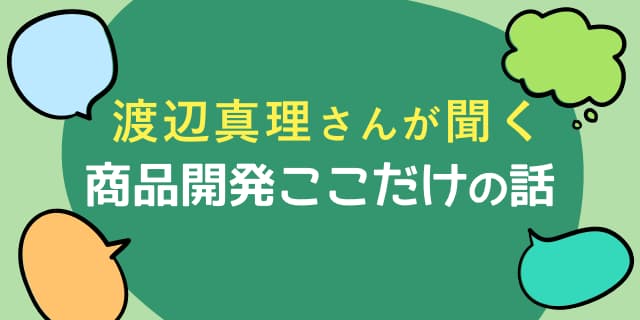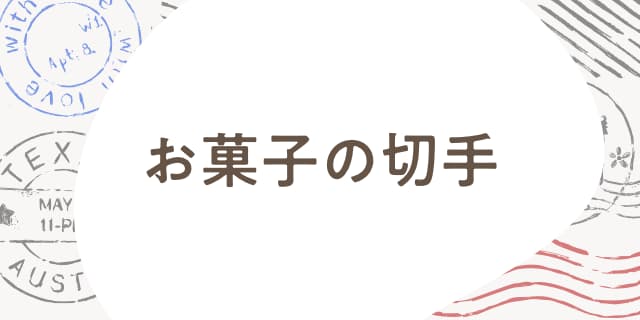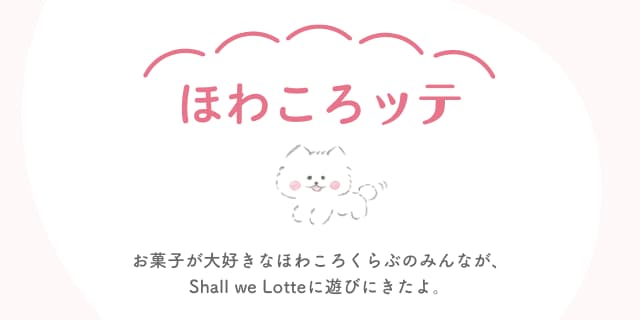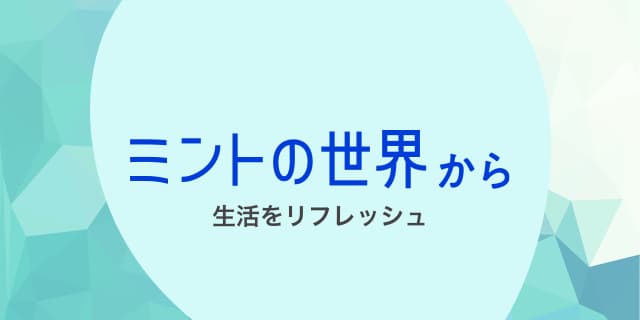タヒンハルヴァ〔ボスニア・ヘルツェゴビナ〕世界中の何にも似てない“ゴマ”のお菓子


知らないモノに出会ったら、迷わず食べたい。そこにはみじんの躊躇(ちゅうちょ)もないし、実際のところ興味しかわかない性分だ。知らないことは知りたいし、食べたことのないモノは当然食べてみたい。今も昔も、そんな“好奇心”が私を形作っている。だからこそこれまで世界の様々な場所で、見知らぬ菓子を食べ続けてきたのだ。
フランスに住んでいた頃、トルコから輸入された「タヒンハルヴァ」を市場で見つけて買ってみたことがある。ハルヴァは、アメになるぐらいまで熱した砂糖と水に、ソープワートルーツと言われる植物の根っこを加え、ゴマのペーストと合わせて型で固めて作る。「タヒン」とはゴマのペーストのことで、中東にはこんなお菓子があるのかと気になって食べてみたのが始まりだった。見た目は薄茶色のただの塊なのだが、シャクッとした食感とゴマのコクが、何とも言えないおいしさなのだ。世界中のどんな食べ物にも似ておらず、とても衝撃的だったことを覚えている。

そんなタヒンハルヴァと再会したのは、ボスニア・ヘルツェゴビナだった。自転車でクロアチアからモスタルという小さな町に入り、首都サラエボへと向かう。フランスから続いた自転車旅のルートの中で、初めて中東文化に触れたのがこの国だった。他のバルカン諸国に比べ、特にオスマン帝国の影響を受けており、首都に至ってはトルコの町並みをほうふつとさせるほど。食事も、ヨーロッパとは全く違う。お菓子屋も同様で「トゥファヒエ」というりんごを煮たお菓子、「フルマシッツァ」というクルミを使ったお菓子など、ボスニアでしか見たことがない個性的な郷土菓子が並んでいた。そしてそれらはどれも、シロップに浸かっているのだ。クッキーでさえもシロップ漬けが定番で、そんなお菓子は、ヨーロッパにはまず無い。菓子にもトルコの影響が色濃く残っているようだった。当然とても甘いのだが、意外にもくどくなくすっきりしていて、私好みの甘さだった。

ハルヴァのお供はボザ
サラエボは数日で回り切れるほどの小さな町なので、町中の全てのお菓子屋に足を踏み入れた。ここで初めて、ハルヴァの専門店を発見。入ってみると、狭い空間に中年のおじさんたちが集っている。英語は通じなかったが、旅で鍛えられたコミュニケーション力で、ハルヴァのお供には「ボザ」という飲み物がおすすめだということが分かった。初めて足を踏み入れる場所には、初めて出会うモノが必ずあるからおもしろい。
ボザは、トウモロコシ粉を発酵させて作る飲み物で、それまで聞いたことも見たこともなかった。乳酸菌ではないそうだが、甘酸っぱい味がまたおいしくて、ハルヴァの甘さをボザの酸味がスッキリとまとめあげ、2つは本当に相性がよかった。気がつけば、サラエボのお菓子屋には必ずボザが置いてあり、みんな満足げにそれを飲んでいる。私もここで初めて出会ってから、好きな飲み物はボザと即座に思い至るほど、好きになった。

初めて専門店で食べたハルヴァは、量産型ではなく手作りで、よりおいしく感じられた。種類はタヒンとココアの2種。専門店でも、どこもそれくらいのラインナップだったのだが、イスラエルで20種ほど並べている店を発見した時は、さすがに驚いた。中東のハルヴァはタヒンがメイン。しかしハルヴァという食べ物は、実に世界の広範囲で食べられているのだ。ロシアはひまわりの種が主流だし、トルコにはチーズのハルヴァ、アゼルバイジャンにはクルミのハルヴァ、インドにはニンジンのハルヴァもあったりと、なかなかに奥が深い。

ボスニア・ヘルツェゴビナは、現地のテレビ取材を受けたり、初めて盗難に遭ったりした国で、衝撃的な思い出がたくさんある。それにもかかわらず、いつでも私の心の中にまず思い浮かぶのは、親切な人々とボザと、口の中で溶けていく何とも言えないハルヴァのおいしさなのだった。
2022-02-01