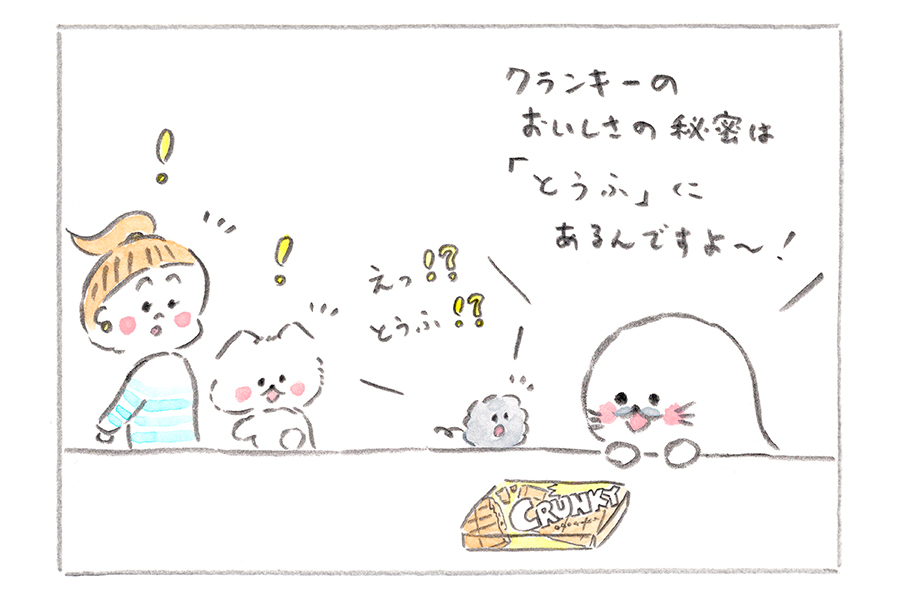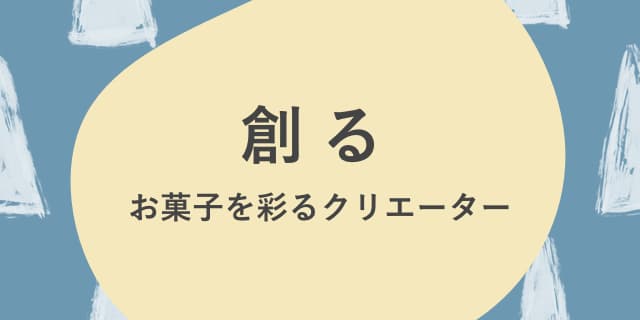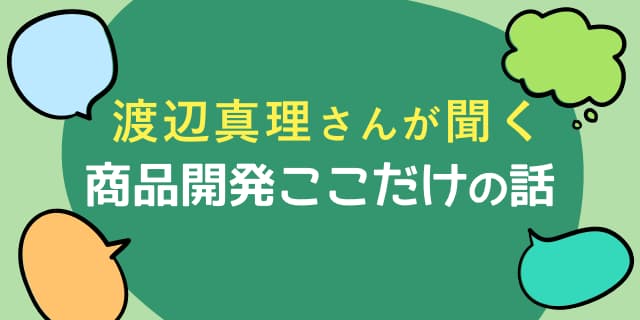茶の湯文化とともに花開いた上生菓子

菓子自体に水分が30パーセント以上含まれているものを“生菓子”と呼びますが、そのなかでも上等なものは“上生菓子”に分類されます。
上生菓子の代表的な存在として知られる練り切り(正式には“練り切り餡”)は、基本的には、白餡に砂糖や山の芋やユリ根、みじん粉(もち米を蒸し、乾燥させて粉にひいたもの)などのつなぎ食材を加えて練った、練り切り餡を主原料としたものです。なお、練り切りのつなぎには、高級なものではヤマトイモや葛が使われますが、これらは味が良いものの傷むのが早く、商品としては扱いにくいため、一般には求肥をつなぎに使った商品が主流となっています。
江戸時代は、茶の湯文化の発展と併せて、砂糖が国産化されたという点でもお菓子の歴史にとって画期的な時代でした。
江戸時代の初期の1623(元和9)年、琉球王国の産業基盤を築いた士族の儀間真常は、当時の明に使いを送り、砂糖の製造技術を学ばせ、琉球独自の黒糖製造に成功しました。以後、南西諸島で原料となるサトウキビ栽培が盛んになり、薩摩を経由して日本の本土にも黒糖が入ってきますが、それでも、当時日本国内で消費される砂糖の大半は輸入品で、長崎に陸揚げされた砂糖の大半が大坂の問屋(当初は薬種問屋、のちに砂糖問屋)へ運ばれ、そこから全国へ出荷されていました。
このため、砂糖の代金として金・銀・銅が国外へ流出することを懸念した幕府は、1715(正徳5)年、貿易に関する制限を行うとともに、サトウキビの作付けを諸藩に奨励。以後、西南日本の気候温暖な地域で“和糖業”が広まり、1798(寛政10)年には讃岐(香川県)の砂糖(和三盆)が大坂の中央市場に出荷されるまでになり、砂糖が生活の中に普及していきました。
こうした背景の下、文化人や茶人が多く生活していた京都では見た目が美しい和菓子が多く生まれます。その中でも小麦粉をつなぎにして蒸す過程を経る“こなし”と呼ばれる和菓子が生まれ、これが関東でアレンジされたものが、現在の練り切りの原型になったと言われています。
お茶席でも供されることの多い練り切りは、職人たちが技巧と趣向を凝らし、四季折々、さまざまな意匠のものが作られていますが、1月から2月にかけては椿をかたどったものが人気となります。
江戸の町で愛された椿
椿の花色は白斑、覆輪(ふくりん)、絞りなどに大きく分類され、花の形も一重咲き、八重咲きの二系統があって、その姿はバラエティーに富んでいますので、練り切りも創意工夫を凝らしたものが多く作られています。今回ご紹介しているのは、“椿をかたどった上生菓子”の切手で、2018(平成30)年10月24日に発行された和の食文化シリーズ第4集の1枚で、あでやかな紅椿が再現されています。花芯の先の花粉の粒はケシの実でしょうか。
ちなみに、首がぽとりと落ちる椿の落花は縁起が悪いとして、武家屋敷では椿を忌み嫌ったという俗説があります。しかし、1613(慶長18)年に記された『武家深秘録』には「将軍秀忠花癖あり名花を諸国に徴し、これを後園吹上花壇に栽えて愛玩す。此頃より山茶(ツバキ)流行し数多の珍種を出す」との記述があり、江戸では椿が将軍家の庇護を受けて武士、町人を問わず愛されていたようです。
実は、「椿は縁起が悪い」という俗説は、明治以降、東京に出てきた薩長の出身者に椿を好む者が多かったことから、彼らの“やぼ”を揶揄(やゆ)するために江戸っ子たちが言い出したものだと考えられています。最初に誰がそう言い出したかまでは確認のしようがありませんが、案外、椿の練り切りを前に毒舌家の茶人たちが言い出したのかもしれません。
2023-01-03