災害と口腔ケア
主催:読売新聞東京本社、NPO法人 ハート・リング運動
後援:厚生労働省、日本医師会、日本歯科医師会、日本看護協会
協賛:株式会社ロッテ 制作協力:一般社団法人 口の健康と食べる力を支える会
災害時は口腔環境にどのようなリスクをもたらすのでしょうか。昨年の能登半島地震で自らも被災した、公立能登総合病院歯科口腔外科の長谷剛志先生の体験を伺いながら、口腔管理、老年歯科が専門の菊谷武先生、羽村章先生を交え、起こりうるリスクや平時からの備えについてオンライン鼎談を実施しました。
→ 講演の詳細がご確認いただけるHPはコチラ
オンライン特別鼎談
災害現場における口腔環境リスクとその対策
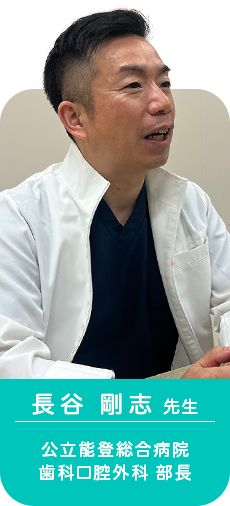


目次
断水とストレスによる口腔乾燥や口内炎が多発
長谷 地震による直接的被害に加え、被災した我々が苦労したのは、3カ月に及ぶ断水でした。限られた水はトイレ用や飲料水に優先され、どうしても口腔ケアは後回しに。そこに極度の被災ストレスが加わり、口腔乾燥や口内炎、舌痛を訴える中壮年層の患者さんが急増しました。
菊谷 震災で大きな影響を受けるのは、これまで高齢者と言われてきましたが、働き盛り(責任世代)に大きなストレスがあり、その影響が口腔に見られたことが驚きです。
長谷 節水するためにトイレの回数を減らしたいから飲食を控える、といったことも起こり、食欲の減退や栄養不足も口内環境に影響したと思います。高齢者の場合は、これらによる脱水・便秘も多く見られました。
菊谷 高齢者の場合、もともと便秘を起こしがちです。水を飲まなければ便秘になり、食欲が低下して、食べる量の減少、低栄養の原因になりそうですね。
長谷 そうですね。口腔環境の悪化や摂食嚥下機能の低下、低栄養などが重なれば、誤嚥性肺炎など呼吸疾患による関連死にもつながります。実際、断水地域では誤嚥性肺炎患者さんが増えました。
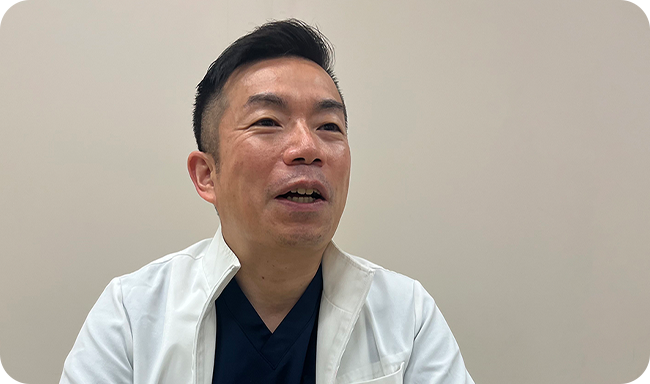
長谷 剛志(はせ・たかし)
2001年北海道医療大学歯学部卒業、06年金沢大学大学院医学系研究科修了。医学博士。09年公立能登総合病院歯科口腔外科医長、15年より現職。能登半島地震では自身も被災する中、様々な取り組みを行っている。
仮設住宅で起こっている新たな口腔環境の問題
長谷 私たち歯科チームは震災1週間後に、どの避難所にどんな口腔の悩みを抱えている方がいるのか調査を行い、医療支援に入りました。その後、被災者が仮設住宅に入居しはじめた4月あたりから、生活的な歯科支援に移行しています。
菊谷 口腔ケアが後手になりやすい有事にそうした活動ができたのは、普段の取り組みを通して口腔環境の重要性が地域の人々に浸透していたからだと思います。
長谷 現在は、以前から活動していた歯科医療者や管理栄養士、言語聴覚士など多職種で編成した「食力の会」というチームで仮設住宅を巡回しています。歯科医療難民になった方、低栄養や摂食機能低下に陥っている方、話す機会が極端に減った方など、孤立による口腔環境の悪化が新たに起きていることに注視しています。
菊谷 住み慣れた家で上手に暮らしていた認知症患者さんが、環境の変化によって症状が顕著になることもありますよね。 長谷 地震のショックによるせん妄もあると思いますが、不安定な行動・心理症状が現れた話は少なからず聞いています。

菊谷 武(きくたに・たけし)
1988年日本歯科大学卒業。同附属病院口腔介護・リハビリテーションセンター センター長を経て、2010年教授、2012年より現職。日本老年歯科医学会副理事長、日本口腔リハビリテーション学会理事長。
災害から身を守るだけでなく、その後の避難生活の訓練も

羽村 今、実施されている避難訓練のほとんどが災害時に身を守る訓練ですが、その後の被災者の健康や生活を守るための訓練も非常に重要ですね。
長谷 そう思います。非常時の口腔ケア、介護食の備えなど、できることはいろいろあります。口腔乾燥対策にはガムを噛むことが有用ですが、唾液がでるだけでなく、体の緊張がほぐれるという声もありました。ガムといえば、今、被災者の方々の口腔機能を評価するために「咀嚼チェックガム」を使っています。
菊谷 「咀嚼チェックガム」は、咀嚼機能や食べ物を飲み込むための食塊形成ができているか、唾液が十分出ているか、義歯が合っているかなど、色の変化や出方で、さまざまなことが判断できますからね。歯につきにくい材料で作られていて、義歯の方でも噛みやすいことも大きな特長です。
羽村 平時と比べて口の健康状態はどうなのか、自分で判断できるように、普段から「咀嚼チェックガム」で確認しておくのも大切かと思います。
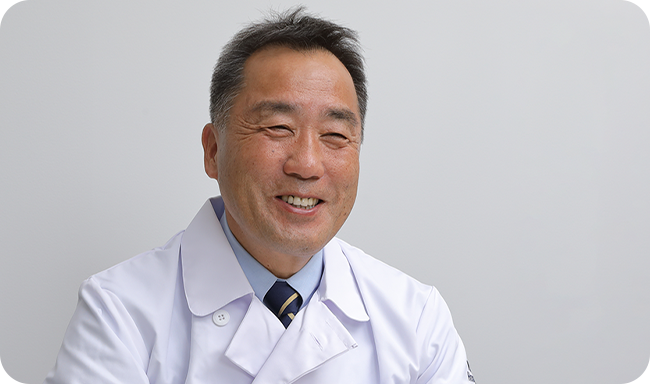
羽村 章(はむら・あきら)
1979年日本歯科大学卒業、83年同大学院歯学研究科修了。同生命歯学部高齢者歯科学教授、同附属病院長、同歯学部長を経て、2023年より現職。日本私立歯科大学協会会長、歯科医療振興財団理事長ほか要職を兼務。

【インタビュー】
羽村先生が解説!非常時のためにこそ、日頃の口腔健康管理の徹底を
非常時には後回しになりがちな口腔ケアですが、口腔の健康は全身の健康にもつながっています。水や物資が限られる中、どう口腔環境を保つのか、平時からの備えが大切です。
水が使えない時は「デンタルフロス(フロス)」が役立ちます。ティッシュなどで汚れが拭えそうな箇所は拭い、歯と歯の間などはフロスで取り除きます。ただしフロスは少しコツが必要なので、歯科衛生士の指導のもと、使い慣れておきましょう。うがいができない状況で歯ブラシを使う時は、そのまま磨いて唾液とともに汚れをペッと吐き出すだけでかまいません。ガムも緊張をほぐし、口腔内の乾燥を防ぐので有効です。選ぶ際は、キシリトール配合のシュガーレスタイプが良いと思います。
非常時の口腔ケアは実践して慣れておくことが重要なので、必ず試すようにしてください。また、口の中を普段から良い状態にしておけば、少々ケアが不十分でも悪化しにくい口腔環境を作ることができます。きちんと定期健診を受け、かかりつけの歯科医師と相談しながら、自分に合った口腔ケア方法を見つけてくださいね。
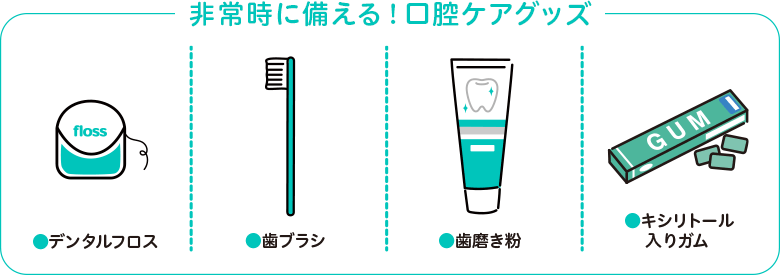
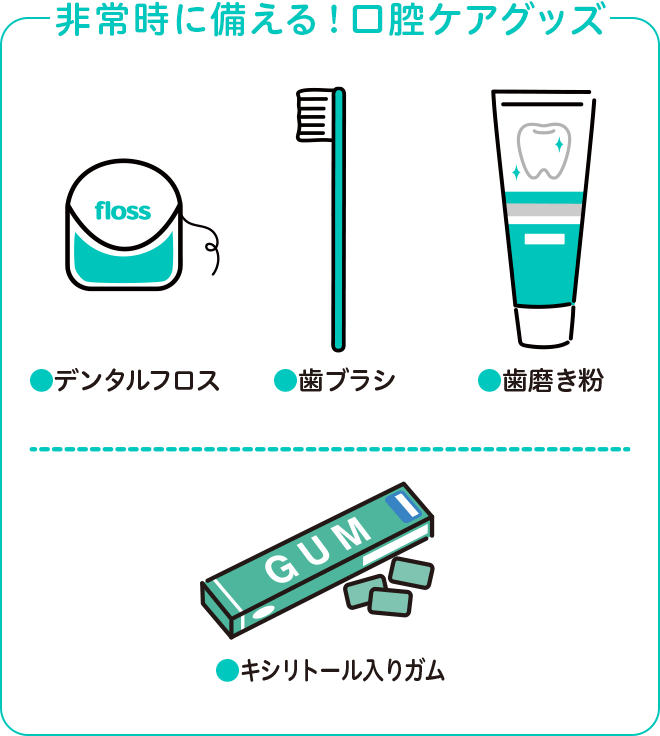
他にも健康二次被害を防ぐための無料動画セミナー公開中!▼
口腔健康サポーター市民講座 いのちと健康を守る口腔ケア

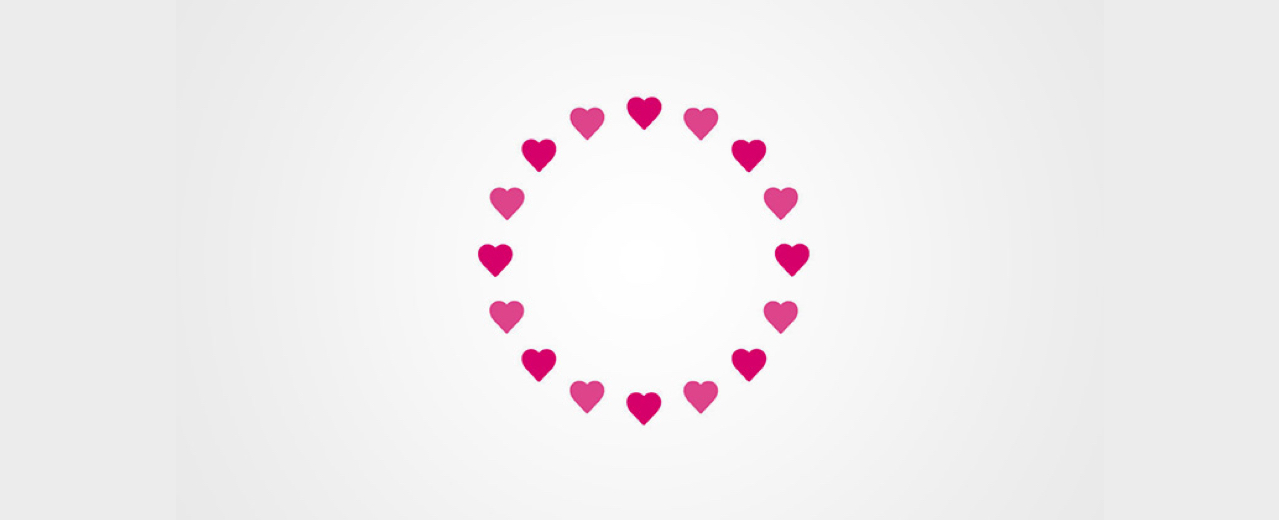
 シェア
シェア ツイート
ツイート





